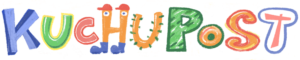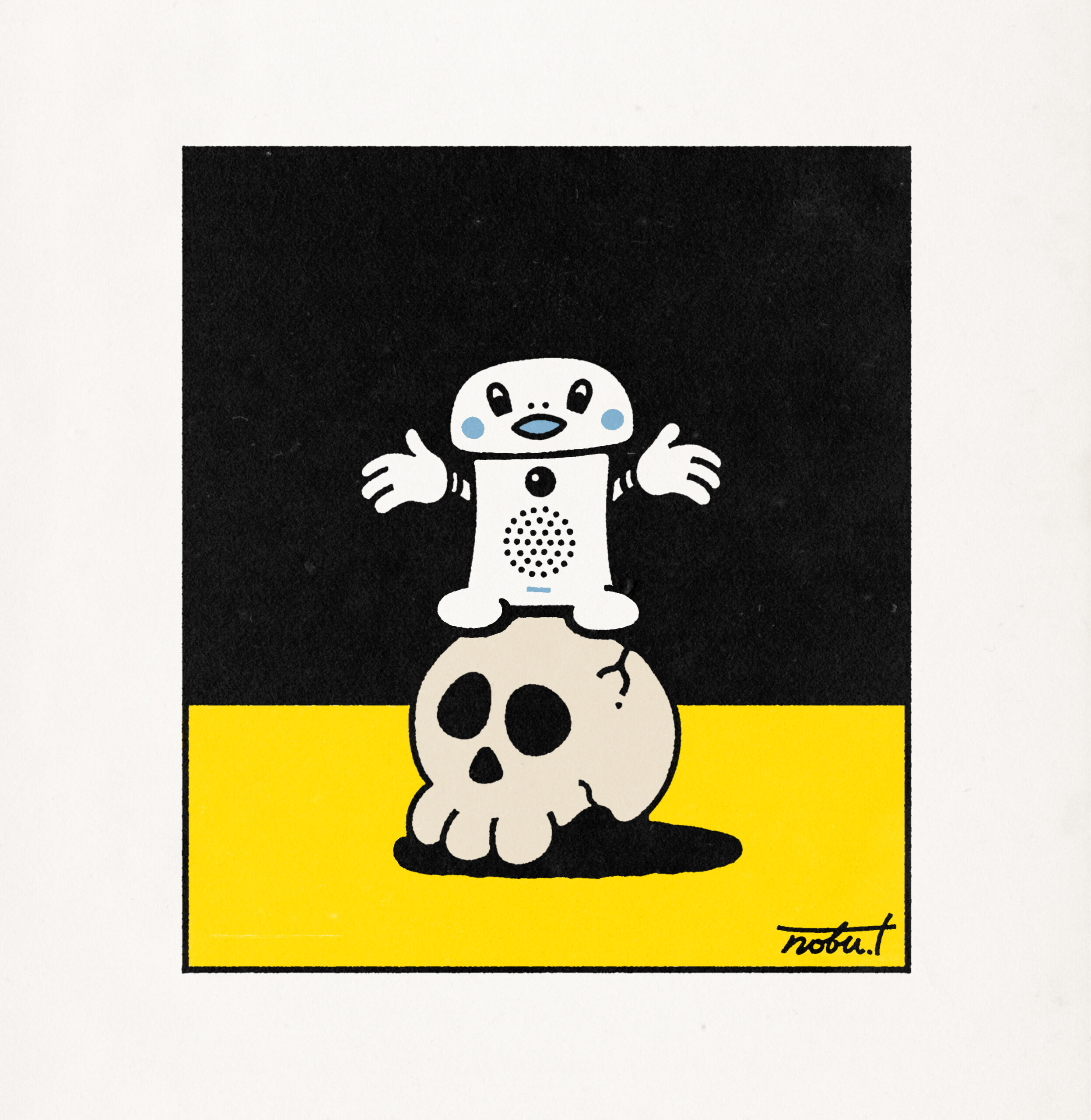『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』は、来年の今ごろ公開予定だ。
僕は楽しみにしすぎており、たまに『ドゥームズデイ』を観た、という夢を見る。
先週見た夢も結構リアリティがあったが、メインキャストの一人がオダウエダの植田さんだったので、現実ではないと気がついた。
ちなみに植田さんはX-MENのメンバーだった。ハマり役だったので、「ちぇ、夢か・・・」と少しガッカリしてしまった。
12月17日現在、今作は予告編すら発表されていない。
マーベルスタジオにいけずを喰らっている状態である。
我々ファンにとって、予告編は一大コンテンツだ。
せいぜいが90秒の新規映像で、ドッグランに連れてきてもらったコーギーくらいハシャげる。
短くて可愛い手足をバタつかせ、場合によってはよだれも垂らす。
キャプテン・アメリカがミサイルでサーフィンしたらシッポを振るし、別世界のドクター・ストレンジが登場すればお腹を見せて喜ぶのだ。
そういう訳で、大勢のファンが『ドゥームズデイ』の予告編を今か今かと待っている。
となると、必ず起こるのは【リーク合戦】だ。
まず、自称・関係者のSNSアカウントが大量に発生する。
有力なリーク(タレコミ)情報を持っているよ、フォローしてね、というわけだ。
彼らの持つ情報は虚実入り乱れているため、基本的には信用できない。
SNSは投稿の反応の大きさでお金を稼げるプラットフォームだ。
そして、巨大なファンダムは新しい情報に飢えている。
間違った形ではあるが、需要と供給が嚙み合ってしまうのだ。あらあら。
それでも、数年前はかわいいものだった。
リークアカウントはPhotoshopやBlenderを駆使し、それっぽい画像を一生懸命作って投稿していた。
いまや、AIでリーク画像・映像は作りたい放題だ。
低コストで、時間もかからないAIの登場で、今年は山ほどフェイク情報がタイムラインに流れてきた。
偽の撮影風景、偽のコンセプトアート、果ては偽の本編映像!
しかもハイクオリティ。3年前なら信じていただろう。
いや、正直言ってもう見分けはつかない。言語化すら難しい、わずかな違和感だけが頼りだ。
もうウンザリ!と言いたいところだが、リークアカウントはあんまりブロックしないことにしている。
楽しみな映画の新情報の真偽で右往左往するのは、なんというか、好きなのだ。
AIの参入は、間違い探しの難易度が上がっただけとも言える。
結局、映画が面白いかどうかは本編を観ないとわからない。当然だ。
予告編や事前情報などはマーケティングの一環に過ぎず、映画そのものとはあまり関係ない。
どっちでもいい。でも、どっちでもいいことで騒ぐのは楽しい。
嘘か本当かわからないが、『ドゥームズデイ』のティザー予告は4つあり、『アバター/ファイヤー・アンド・アッシュ』の上映時に、毎週違う予告映像を流していく、という噂がある。
本当だとしたら、とんでもなく大胆というか、アホなやり方だと思う。
本当だといいな。