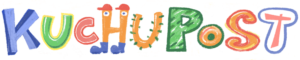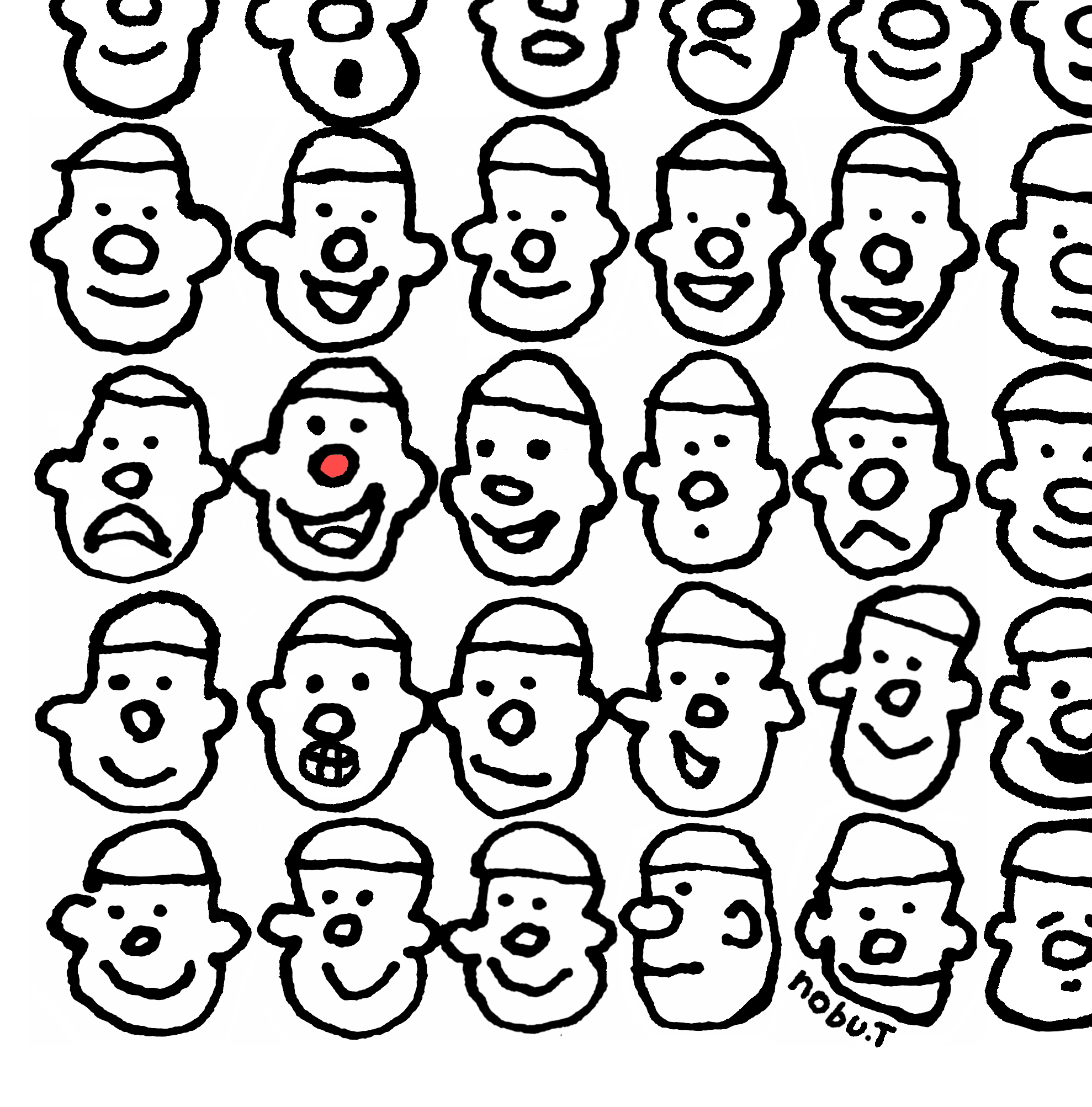2022年8月、後輩の大原(仮名)から聞き取った話です。
なんていうか、いまだによく分からない話なんですけど。
母方の祖母のお姉さん、アキコ大叔母さんってのがいたんですね。
4年前くらいに、大掃除したんですよ。アキコさんの家を。
当時で80歳くらいだったんですけど、割と元気な人で、早くに旦那さん亡くして以降は一人で達者にやってて。
とはいえ、結構モノも増えてきてるし、一回しっかり大掃除しようか、って話になりまして。
僕と母でアキコさん家を訪ねたんですよ。
まあ普通に、要るものと要らないもの分けて、窓拭いて、床掃除して…、ってやってたんですけど。
床下収納、って分かります?
キッチンの床にたまについてるやつ。― そうそう、それです。四角いフタがあって、取っ手がついてて。
ソレがアキコさん家にもあって。
ここも掃除しよう、と思って、取っ手を引っ張るけど開かないんですよね。
で、アキコさんに聞いたら、「あー、そこ開かんのや。」って言うんですよ。
数十年前に中古でこの家を買った時から、一度も開けたことないんですって。
確かに、なんかフタの周りが汚れで固まってる感じでした。
でも、中でカビとか生えてたら気持ち悪いじゃないですか。アキコさんも「開くなら、掃除できたらええけどなあ。」って言うんで。
フタの周りに洗剤かけて、雑巾でくるんだハンマーで、フタをちょっとずつ叩いて…、ってやってたら、ガパッて開いたんですよ。
空っぽでした。収納用のプラスチックの、深めのトレイがあるだけ。
なんですけど、もう、プラスチックに見えないんですよね。
底の方、お札がびっしり貼られてたんで。紙製のトレイか?って思うくらい。
貼られ方も尋常じゃなくて、もう10枚とか20枚じゃきかない。お札の上にさらにお札貼って…、って感じで。
そんなん見ちゃったから、アキコさん、もう悲鳴上げて嫌がって。
でも、「もうそれ剥がさんでええから!」って言うんですよ。
剥がして変なことが起きても怖いから、って。
確かにそうですよね。これを貼った誰かも、”変なこと”が起きたから、こんな風にしたんでしょうし。
だから、フタを戻して、その上からテープでしっかり目張りして、その話は終わりにしたんですよ。
去年、アキコさんが亡くなりまして。
死因は全然普通、って言ったら変ですけど、出先で心臓麻痺で倒れて、っていう。
僕と母と祖母の三人で、アキコさん家を片付けに行ったんですけど、例のお札どうする?って話になるじゃないですか。
お札って貰ったところに返さなきゃいけないらしいんですけど、前見た時も梵字?みたいなのが書かれてることしか分からなかったんですよね。
どこの、なんのお札なのか、まったく見当つかなくて。
まあ、祖母が知ってる神社に相談したら、不明のお札もとりあえずお焚き上げしてくれるそうで。それは良かったんですけど。
ってことは、剥がさないと…なんですよね。
メッチャ嫌でしたけど、テープ剥がして、フタ開けて。
当然貼られてますよ、お札が大量に。
なんか湿気で黄ばんだり、ポロポロ崩れてるやつもあったりして。
でもしょうがないんで、手を突っ込んで、できるだけ丁寧に、一枚ずつペリペリ剥がして。
怖いから、ちょっと薄目気味でね。
こんなに頑張ってんのに、祟られたら理不尽だな~、とか思いつつ、床にそっと置いていったんです。何枚も、何枚も。
そしたら、
「えっ」「ひいっ」
って聞こえて。
母と祖母の声でした。
俺が置いたお札を揃えようと、手に持ったんですね。
お札の裏面を見ながら、
「なんか、書かれてる。全部同じことが書いてある。」
って母が言うんです。
えっ、と思って、手元に目をやると、剥がしかけたお札の裏が少しだけ覗いてて。
「◼️◼️、ごめんね」と書いてある、ように見えました。
明らかに人がペンで書いた字でした。
「アキコの字だ!これ、アキコの字だよ!」
祖母がわなわな震えながら、お札の裏を見てそう言うんです。
でも、意味わからなくないですか?
アキコさんが、いつこれ書いたんですか?
僕らが大掃除したあと、一人でフタを開けて、お札を剥がして書いたんですか?
それとも、家を買ったとき、最初からってことですか?
そもそも、書いてあることも意味不明なんですよ。
蛍光灯に照らされると、はっきり読めました。
「まーちゃん、ごめんね」
祖母も、母も、”まーちゃん”が誰なのか、まったく心当たりがないそうです。
そこまで話すと、大原は急にむせ始めた。
「大丈夫?」
「いや、すいません。ゲホッ。なんか、この話すると、胸の辺りがつっかえる感じがして、気持ち悪いんですよね。気のせいだとは思うんですけど。」
ほら、この辺。
<了>