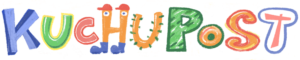父が車のウインドウから腕を出し、砂を捨てた。私が6歳のときの記憶だ。
人通りの少ない住宅街。砂はキラキラ輝いて空中に消えていく。後部座席の窓ガラス越しに、私はそれを目撃している。
サラサラ。サラサラサラ。サラサラサラサラ。いや、多くない???
全然終わらない。なにが起こっているのか分からなくて、そっと運転席の父の顔を伺う。完全な無表情。
チャイルドシートから少し身を乗り出して、父の右手に目を移す。まだ砂出てる。
父の手は確かに大きいが、そんな量の砂が格納されてるわけがない。
そもそも、なんの砂? まるでテレビで見た沖縄のビーチみたいに、真っ白できれいな砂に見える。
だが、いまはコープで洗剤を買った帰りだ。コープで砂、見たことない。
「お父さん、それなに?」と聞けば済む話だが、子供ながらなんとなく気が引けた。本当に海の砂に見えたから。
父は、砂浜がとても嫌いなのだ。なぜかは知らない。最低の思い出がある、らしい。
その苦手ぶりは筋金入りで、ディズニーシーがワイドショーで特集されているだけでチャンネルを変える。あそこに砂浜ないのに。
『プライベート・ライアン』も観ない。冒頭に海岸での戦闘シーンがあるからだ。
人がグロく死んでいく様子より、そのロケーションが駄目らしい。
パッパッ、と右手をグーパーさせたあと、父は窓を閉めた。終わったようだ。
「なあ、美伊子。」
急に声をかけられて、私はハッとする。
不思議と緊張してしまう。別に悪いことはしてないのに、なんとなくバツが悪いのはなぜだろう。
「なに、お父さん。」
「あのさ、やっぱりお昼、外で食べない? 国道沿いにフレッシュネスバーガーっていうお店が出来たんだよ。お父さんとそこでハンバーガー食べないか。」
えっ、ラッキー。
突然のハンバーガーチャンスに、すべてを忘れて心が躍ってしまった。砂とかどうでもいい。
「マックナゲットあるかな?」
「あるかもよ。」
父は笑いながらハンドルを切った。
******
父が運転する車の助手席で、その記憶がよみがえった。はるか昔、ほとんど30年前くらい。そんな奇妙な体験をした、ような。
平日でもそれなりに埋まっているパーキングに、父は妙にゆっくり駐車する。二人で車を降りると、生暖かい風が私たちを迎えた。
鎌倉の海岸に、私たちは初めて親子で訪れたのだ。
ここに到着するまで、会話らしい会話もなかった。
会うのも数年ぶりなので、積もる話は一応あるのだが、どれも楽しいものとは言い難いせいで、自然と口も重くなる。
好きなアニメの劇場版が制作中止になったこと。熱帯魚を育ててみたけど全然うまくいかないこと。結局子供はできなかったこと。離婚したこと。
別に落ち込んでいるわけではない。私は元気です。気が重いだけ。
一人暮らしの手筈も整っているし、仕事もうまくいっている。元夫と関係が悪いわけでもない。
センチメンタルな気持ちや、相談ごとがあって父に会いに行ったのではないのだ。
ただの気分。
人生が変わる節目ですし、一応会っといたほうがいいか、みたいな。
だけど、実家の玄関先で顔を合わせたとたん、父はこう言った。
「海に行こう。」と。
到着した海岸は広く、夕方でも人がまばらにいた。犬を散歩させる人、カップル、サーファー。
海を見つめる父の背中からは、なにも読み取れなかった。あんなに嫌っていた砂浜が、小さい坂道を降りればすぐそこだ。
マジでなんのつもりなんだろう。私を励ましたいんだろうか。
春先の海風は、まだ少し冷たい。気持ちはありがたいが、来たばかりだというのに私はもう帰りたかった。
「お父さん、ありがとう。無理しなくていいよ、帰ろう。」
そう言おうとした瞬間、父が走り出した。初老とは思えないスピードで。
腕をしっかり振りながら、坂道を転げ落ちるように下り、砂浜に着地。こちらを振り返ることもなく、海岸線を駆け抜けていく!
なにが起きているかわからず、一瞬体が固まったが、私もすぐに走り出した。追わないとヤバそうだ。そう直感した。
「ちょっと、お父さん!待って!!」
絶対聞こえているのに無視して、父は走り続ける。が、数十メートルも走らないうちに、明らかにペースダウンしていき、ついには仰向けにバッタリと倒れこんだ。
「おっ、お父さん、大丈夫!?」
ぜえっ、ぜえっ、と疲労感も露わな呼吸をしながら、ヨロヨロとオッケーサインを見せる父。
おじさんの全力の奇行に興味を示したのか、散歩中のコーギー犬が近づいてきて、顔を嗅がれている。
飼い主は「こんにちは~」と朗らかに挨拶し、父も「はぁっ、はっ、こん、こんにち、は~~!」と返事をする。
なにからなにまで、意味不明だ。
満足したコーギーと飼い主が去っていくのを見送って、私は父に向き直った。
「意味不明だよ、お父さん。」
「フゥーっ、フゥー…。だよなぁ。」
以前、大の字に寝転がったまま、ハハハ、と父は笑った。
「美伊子、これは初めて人にいうんだけどさぁ。お父さんな、一個だけ超能力あるんだ。」
「はぁ?」
「小さいころ神様に会って、人生で一回だけ使える超能力をもらったんだ。で、いま使ってるんだよ。」
なんだろう、ボケてしまったんだろうか。それとも冗談を言ってるのだろうか。
ヘラヘラ笑う父の表情からは真意を読み取れず、とりあえず私はしゃがみ込む。
「…どんな能力なの、それって。」
「過去に、好きなモノを送れるんだよ。なんでも送れる。一回だけな。それで、いま、砂を送っているんだ。ほら、見てみろ。」
そう言いながら、父は砂を握って自分の手のひらに乗せた。途端に、パッと消える。もう一度乗せる。また消える。
「な、本当だろ? それに、ホラ! 立て、美伊子、立て。」
あっけにとられながら立ち上がる私に、父は嬉しそうな顔で向かい合う。
「見てみ。こんなに暴れたのに、服も肌も、髪も、ぴかぴかだろ! 砂で汚れると掃除が本っ当に面倒だけど、もう過去に送ったからな。心配ナシって訳だ。」
背中も、靴も見てくれ、ほらほら。
言われるがまま観察するが、確かに。自分のスニーカーは内も外も砂まみれだが、父の革靴には砂粒ひとつついていない。
すべて、あの瞬間。私が6歳のときに見た、ドライブ中の父の右手に転送されている、ということなのか。
ていうか、ていうか。
「ていうか、なんでそんなことに使うの? な、なんだかわかんないけど、もっとすごい事とか、ピンチのときに使えばいいのに!」
狼狽する私をよそに、父は「いいの、いいの。」と笑うばかりであった。
つられて、もうどうでもよくなって、私も吹き出してしまう。
「ククッ、フフッッ…。マジで、なんなのそのパワー。そんなのアリ?」
ありだよ、美伊子。なんでもあるんだよ。
この世はなんでも起きるよ。
見せつけるようにジャンプを繰り返す父の向こう、水平線に太陽が落ちていく。
夕焼けに照らされて、空中に舞った砂がキラキラと輝いていた。
<了>